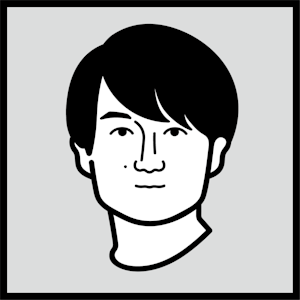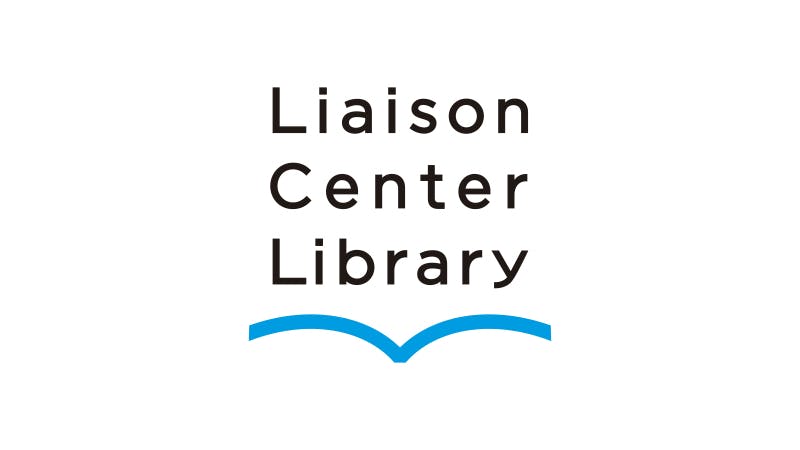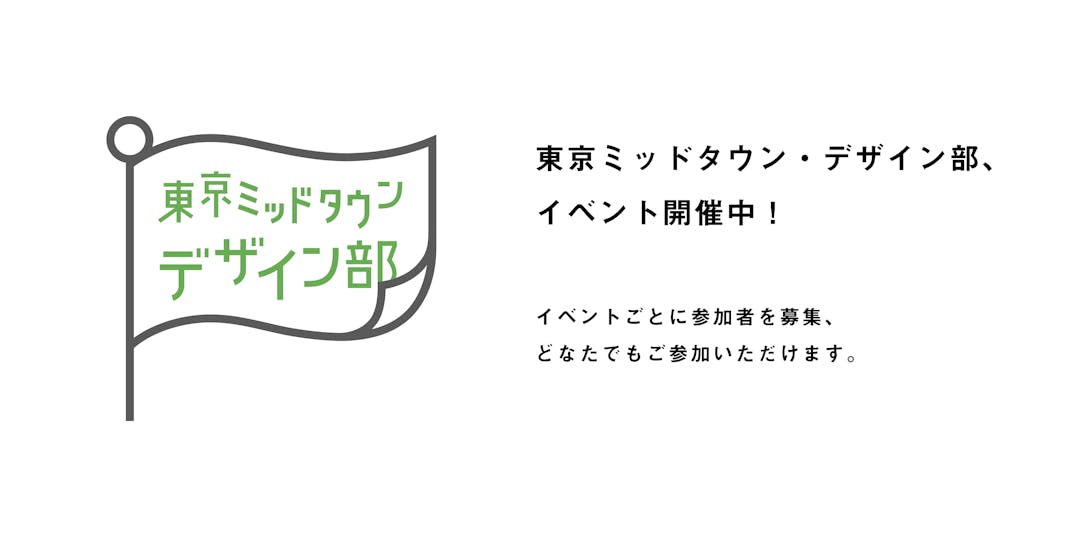はじめの一歩から ひろがるデザイン展 関連イベント
デザインと人類学/哲学──人文学との行き来から見えてくるものとは?
- 開催年:2025
デザインと人類学/哲学を行き来する両者の対話から、その相互交流が生み出すもの、そしてこれからのデザインの展望を語り合う
昨今、「人類学」や「哲学」といった人文学に創造性のヒントを求めるデザイナーが増えつつあります。一方で、人類学者がデザインの現場に参画する「デザイン人類学」、また大学の外での対話を主とする「哲学対話」などの実践をはじめ、人文学の側から「デザイン」に目を向けるケースも出てきています。
こうしたデザインと人文学の行き来は、グッドデザイン賞の審査の過程を通じて得たインサイトを、これからの社会に向けての提言として発表する取り組み「フォーカス・イシュー」の本年度の提言内容とも通底します。中でもデザイン人類学者・中村寛さんの提言「内なるクリエイティヴィティとともに、自然-文化-経済のエコシステムを脱植民地化する」においては、「自然-文化-経済の不可分性をデザインのなかで実現している試みが他領域にもさらにひろがるよう、(特に人文学の)研究者とビジネスの協業体制をさらに深めていきたい」と書かれています。
こうした動きについてより議論を深めるべく、今年度の提言とその中で取り上げられている受賞作を紹介する展示「はじめの一歩から ひろがるデザイン展 - グッドデザイン賞2024フォーカス・イシュー -」(東京ミッドタウン・デザインハブで開催中)にあわせて、トークイベントを開催します。登壇するのは、デザインと人文学を行き来しながら活動する2名。まずデザイン人類学者として、多摩美術大学での教授としての研究・教育活動のみならず、デザインファームKESIKIへの参画やグッドデザイン賞フォーカス・イシューでのリサーチャーなどの活動も積極的に行う、前掲の中村寛さん。そして自身が経営するnewQにて、「哲学事業部」や哲学カルチャーマガジン『ニューQ』を通じて、デザインと哲学を行き来する活動に取り組む瀬尾浩二郎さんです。
デザインと人文学の相互交流はなぜ起きているのでしょうか? デザインと人文学の行き来によって生み出される価値とは?──デザインと人類学/哲学を行き来する両者の対話から、その相互交流が生み出すもの、そしてこれからのデザインの展望を徹底討論します。
日 時:4月28日(月)18:30 - 20:00
会 場:インターナショナル・デザイン・リエゾンセンター
(東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー5階 デザインハブ内)
お申し込み:Peatix
※参加費無料・先着順
登壇者:
瀬尾 浩二郎氏
新しい問いを考える哲学カルチャーマガジン『ニューQ』編集長。リサーチや編集、サービスデザインを専門とする会社、newQ(株式会社セオ商事)代表。哲学の手法を取り入れた「問いを立てるワークショップ」や「概念工学ワークショップ」といった考える場をひらく活動をおこない、さまざまな組織との仕事に携わる。著書に『メタフィジカルデザイン』(左右社)。

中村 寛氏
文化人類学者。デザイン人類学者。多摩美術大学リベラルアーツセンター教授。アトリエ・アンソロポロジー合同会社代表。KESIKI Inc.でInsight Design担当。「周縁」における暴力や脱暴力のソーシャル・デザインといった研究テーマに取り組む一方、様々な企業、デザイナー、経営者と社会実装を行う。多摩美術大学では、サーキュラー・オフィスやTama Design UniversityのDivision of Design Anthropologyをリード。著書に『アメリカの〈周縁〉をあるく――旅する人類学』(平凡社、2021)、『残響のハーレム――ストリートに生きるムスリムたちの声』(共和国、2015)など。

小池 真幸氏(モデレーター)
編集者。人文・デザイン・暮らしといった領域を中心に、研究者やクリエイターと協働しながら、ウェブメディアから紙媒体まで幅広く情報発信やメディアづくり、コンテンツ制作に携わっています。最近の活動場所:一般社団法人デサイロ、PLANETS、designing、DIG THE TEA、MIMIGURIなど。2025年7月、横浜・白楽にて書店(など)開業予定。2024年度フォーカス・イシューレポートの編集を担当。